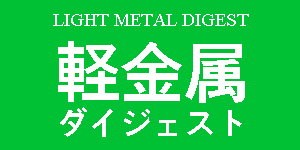
このサイトは、本誌の定期購読契約者のみが利用できるメンバー専用ページです。
 |
NO.1522(2001年02月12日号)
|
古河鋳造
大型新製品量産で収益回復
1650㌧ダイカスト機を増設
非自動車の大型鋳造新製品が本格的に立ち上がってきた。総売上高は横ばい圏ながら、新製品の量産効果で今期経常利益は5,100万円と前期比倍増、来期は2億円を見込む。新製品増産対応で、1650㌧ダイカスト機1台を増設する。
古河鋳造(川崎市幸区、工藤公三社長)の収益が、非自動車部門の大型薄肉鋳造新製品の量産効果を背景に再度上昇基調に入ってきた。2001年3月期決算は売上高が112億4,000万円と前期比5.2%増を確保。収益面でも経常利益は前期比2.1倍の5,100万円の見込み。最終損益も前期の5億4,300万円の赤字から5,400万円の黒字計上となる。
今中間決算は売上高52億2,400万円、経常損失7,400万円、純利益529万円(関係会社の整理益7,700万円を計上)。今下期だけでみると、売上高が60億500万円、経常利益1億2,500万円と上期に比べて収益が大きく回復する。
これは①一体成形のエスカレーター用ステップ②交通信号器③PDP(プラズマ・ディスプレー・パネル)用シャーシのほか、電話器前面パネルなどの新分野製品の量産効果が本格的に現れてきたため。
エスカレーターステップは三菱電機、フジテック・フロンテア、東芝の3社向けに月産5,000台規模で量産。大店舗法の改正を前にした駆け込み需要を背景に生産が膨らんだが、さらに、鉄道駅でのエスカレーター・エレベーターなどの設置を義務付ける「交通バリアフリー法」が昨年11月に施行されたことで、下期には月7,000~8,000台に需要が拡大する見込み。PDP用シャーシも現在、松下電器向けに月間1,500台の生産量。松下の増産体制が整う今年6月頃には4,000~5,000台にアップする見込み。将来的には家庭用に低価格化を実現したPDPの登場で、さらなる需要拡大を期待している。こうした新製品比率は上期で10%強に達している。
一方、トラック向け部品は今上期は横ばい、下期で微増の予想。また、建材のダイカスト製床材も半導体業界の高水準設備を映して、クリーンルーム向けに好調。上期の販売実績8億円強(売上げ構成比16%)から下期は構成比30%強の19億円弱、通年では27億円(アルミ使用量1,500㌧)と前期実績の21億6,600万円から回復。来年度上期でも22~23億円の予想と当分、繁忙状態が続くと見ている。また、トラック向け部品も4~5%の回復を見込んでいる。
このため、2002年3月期業績は売上高は110~115億円の予想ながら、収益面では新製品の量産・増産対応が完了するため、経常利益2億円、最終利益1億2,000万円と大幅に改善する。
同社はダイカスト設備として、3550~1200㌧7台、800㌧8台、500~350㌧6台の計21台を保有しているが、大型新製品の増産対応に、今年7~8月の本格稼働開始予定で、1650㌧コールドチャンバー1台(宇部興産製)を増設する。
なお、一旦白紙にした「工場移転計画」は、新製品の増産対応や、昨年1月にキックオフしたISO9000の認証取得に追われていたこともあり(今年3月までに取得の見込み)、今年9月をメドに新たな計画を策定中。工場移転は2002年にずれ込む模様である。
日軽金が急拠トップ交代
新社長に佐藤薫郷副社長
「構造改革」メドで若返り人事
日本軽金属は1月26日取締役会を開催、4月1日付で松井一雄社長が取締役に退き、佐藤薫郷取締役兼副社長執行役員が社長に昇格するトップ人事を決めた。増田祐孝代表取締役会長は代表権のない取締役会長に就き、取締役会議長を務める。松井一雄社長は6月開催予定の定時株主総会で取締役も退任、相談役に就任する。
同日記者会見した松井社長は「グループ構造改革の着手と実行を終え、負の遺産処理にも目処が付いたのを機に経営陣の若返りを図る」とさばさばした表情。しかし、今3月期に大幅最終赤字・無配転落に陥ることになったのを受けて「けじめを付ける意味もある」という。
社長在任1年9ヵ月で、しかも任期半ばでの突然の社長交代劇。松井社長は「99年12月に『グループ経営構造改革』を発表、翌1月から実行に移したが、94年1月に常任顧問・管理本部長に就任以来の7年余、増田祐孝社長の“特別補佐官”として経営の中枢に携わってきた。社長在任期間は短いものの、密度は濃く、完全燃焼した思いだ。奇しくも今日(1月26日)は65歳の誕生日だが、昨年の夏頃から、社長職の重さ・責任や色々な課題をこなしていくには体力・気力の面で衰えがあってはならないと感じ、早い時期に社長職を引き渡すことを考え始めた」という。日軽金は「グループ内課題事業の再構築」方針により、メモリーディスク事業からの撤退、大阪工場の閉鎖など一連の構造改革を実施した。しかし、柱となる新日軽の経営再建については「残念ながら解決策を提示できない状態で持ち越した」(松井社長)。
松井社長は佐藤副社長を後任に選んだ理由として、「知力は言うに及ばず、腹が座っている」を挙げ、「自分の思うとおりにやって欲しい」と述べた。
一方、佐藤副社長は早くから社長候補として名前に上がっていた“日軽金のプリンス”。同氏も今年10月には62歳となることから、松井社長が早期に退任、社長の座を譲る。記者会見に臨んだ佐藤副社長には笑顔は見られず、終始、固い表情のまま。同副社長は抱負を以下の通り語った。
「『アルミの日軽金』という看板・トップブランドを復活させたい。日軽金は『選択と集中』といいながら、これまでは事業の整理に偏っていたきらいがある。キャッシュフローをもっと増やす必要があるが、そのための施策として実業をキッチリとやり、収益力を上げて復配を果たす。日軽金単独の経常利益は現在30~40億円だが、5円配当をするには100億円の経常利益が必要。そのためには新事業・新商品を増やす必要がある。これまでの日軽金に欠けていたのはマーケットに結びついた新商品・新事業を作り出すことだ。創造性・多様性で会社の文化を変える。中堅・若い人を完全燃焼させる方向で経営を進めたい」
「板・押出等のレベルでの(他社との)統合・提携を行っても強い会社になるとは思っていない。日軽金はアルミ部門の経営資源を使い切っていない。東洋アルミとの合併や化成品・カーボンなど同業他社にないものがあり、事業部を越えた“横の関連”を使い切ることで顧客のニーズに沿うことを経営の課題にしたい」。
新日軽の再建について佐藤副社長は「コストダウン、品質の改善、販売ルート、商品政策の見直しなど自助努力の範囲内で収益がブレーク・イーブンに近いところまで回復させることができよう。共同物流や相互OEM供給など他社との協力を拡大していくことは一つの方向として考えられる」という。「名門復活」の切り札として佐藤副社長に寄せる関係者の期待は大きい。
佐藤薫郷(さとう・しげさと)氏の略歴:▽昭和14年10月生れ。静岡県出身▽37年3月東大法学部卒、同4月日軽金入社▽43年7月ジュネーブ工業経営研修所留学(1年間)▽62年3月製錬事業部営業部長▽63年6月メタル事業部長▽平成3年6月取締役メタルセンター長▽5年2月取締役兼アルコム社社長▽同6月常務取締役兼アルコム社社長▽8年6月専務取締役軽圧本部長▽11年6月取締役副社長軽圧本部長、東南アジア担当▽12年6月取締役兼副社長執行役員、軽圧本部長、東南アジア担当▽13年4月代表取締役社長就任予定。
三菱マ、アルミ缶子会社統合
新会社「新菱アルミテクノ」
三菱マテリアル(西川章社長)は4月1日付で、100%出資のアルミ缶事業子会社2社を統合すると発表した。業務運営の効率化と体質強化が狙い。アルミ缶回収事業を行う新菱アルミ罐回収センター(東京・丸の内、野副明邑社長)を存続会社として、アルミ缶周辺事業を行う新菱サービス(同、植木寛社長)を消滅会社として合併させる。
合併新会社「新菱アルミテクノ株式会社(仮称)」は本社を東京都丸の内一丁目5番1号に置き、社長には植木寛氏が就任する。資本金は5,000万円で100%は三菱マテアルの出資。従業員数は180名で、合併2社の従業員全員が移管する。売上高規模は53億円。
新菱アルミ罐回収センターは今年1月、加工業務をUBC(使用済み飲料用アルミ缶)一貫処理工場を運営する新菱アルミリサイクルに移管済み。アルミ缶周辺業務をアウトソーシングするために平成6年に設立された新菱サービスとの一体的運営によりさらに体質強化を図る。アルミ缶製造の周辺事業の中でも高度な技術を要する新事業へも展開する。
昨年のアルミ圧延品生産出荷
板は過去最高、押出も5%増
日本アルミニウム協会が発表した2000年(平成12年)暦年のアルミ圧延品生産・出荷統計(12月は速報)によると、板、押出ともに2年連続のプラスとなった。板は生産が134万6,379㌧で、前年比2.3%増。出荷が1.1%増の134万6,901㌧で、生産、出荷ともに2年連続の過去最高更新となった。輸出が年初来大幅なマイナス基調で推移した反面、箔、印刷板、フィン材、自動車材、店売り等の内需が高水準を記録、主力の缶材もプラスに転じた。
押出も生産が110万6,632㌧(前年比5.0%増)、出荷が110万6,348㌧(同5.2%増)。非建設分野の半導体製造装置、OA機器、自動車向けが高水準で推移したのに加え、主力の建設向けも増加に転じたことで2年連続のプラスとなった。ただ、生産・出荷ともに過去最高である平成8年(生産125万122㌧、出荷124万7,413㌧)を11%強下回る水準にとどまった。
板と押出の合計では生産、出荷ともに2年連続のプラスながら、過去ピークである平成9年(生産254万5,114㌧、出荷254万9,824㌧)比4%強のマイナス。
一方、箔は主力のコンデンサ向けが高水準で推移、2年連続のプラスになるとともに、平成9年の過去ピーク(生産14万6,391㌧、出荷14万5,598㌧)を3年ぶりに更新した。
12月板出荷、1.3%減
なお、12月単月(速報)では板の生産が10万8,100㌧(前年同月比2.9%増)、出荷が10万6,451㌧(同1.3%減)。生産は3ヵ月連続のプラスで12月としては過去最高。出荷は高水準ながら4ヵ月ぶりのマイナス。押出は生産が9万6,220㌧(同4.8%増)、出荷が9万5,346㌧(同4.7%増)で、ともにプラスは14ヵ月連続。また箔は生産が1万3,887㌧(同10.1%増)、出荷が1万4,051㌧(同8.4%増)。プラスは生産が21ヶ月連続、出荷が22ヶ月連続のこと。12月としてはともに過去最高。
藤井会長は今後の需要見通しについて、「IT関連は昨年12月以降足踏みが見られる。若干の調整局面が予想されるが谷間はそれほど深くないだろう。後半の持ち直しに期待して、通年では昨年並み、ないしは微増になろう」との見方を述べた。
アルミ鋳造メーカーを合併
完成部品調達へ、ヤマハ発
ヤマハ発動機は4月1日付けで、100%出資子会社のアルミ鋳造部品メーカー、津島ダイキャスト(愛知県津島市、宮下健次郎社長)と40%出資の刑部合金鋳造所(静岡県磐田郡、刑部次功社長)を合併し新会社を設立する。また、協会社でアルミ部品精密加工・表面処理メーカーの鈴木鉄工所(静岡県浜松市、鈴木康文社長)に出資し、関連会社とする方針も明らかにした。
合併新会社「株式会社ファインキャテック」の本社所在地は静岡県磐田郡竜洋町小中瀬738、社長には宮下健次郎氏が就任する。新資本金は1億3,450万円でヤマハ発動機の出資比率は約70%となる。
新会社は来年春ごろまでに鋳造と機械加工の工場を本社工場(旧・刑部合金鋳造所)内に増築し、アルミ部品の鋳造から機械加工まで一貫製造する完成部品メーカーをめざす。増築に伴う鋳造設備は津島ダイキャストから移管する。取扱い部品は主として、二輪車のカバーシリンダーヘッドやクラッチ部品などの中・小物アルミ部品となる。
一方、鈴木鉄工所はこれまで、二輪車のクランクケースカバー類の加工・表面処理を行ってきたが、ヤマハ発動機の出資を機に今年春頃までに敷地内に鋳造工場を新設し、クランクケースカバー類の鋳造から加工・表面処理までを一貫製造する完成品部品となる。鋳造設備および鋳造技術は津島ダイキャストから移管・支援する。
ヤマハ発動機は部品調達コストの削減を図るために、従来の鋳造や加工などの工程毎の調達から完成部品を購入する方針に変更。協力メーカーの事業内容を、鋳造から加工や表面処理などまで一貫製造する完成部品メーカーへの転換を進める。
平成12年の軽金属製品生産
88万600㌧、0.1%増
軽金属製品協会は平成12年暦年の軽金属製品生産・出荷実績(一部推定)をまとめた。それによると、生産は88万600㌧、前年比0.1%増、販売は91万7,000㌧、同0.3%減となった。生産量は平成8年の100万3,407㌧をピークに3年連続の落ち込みとなり、昨年は微増となったものの、3年連続の80万㌧台にとどまった。
とくに、器物など日用品は平成3年の1万2,697㌧をピークに9年連続のマイナスで、生産規模は36%にまで縮小した。産業用品や建築用品はほぼ横ばい。
陽極酸化処理も平成8年以降8,000万㎡台で推移していたが、9年には大台を割り込み、10年からは7,000万㎡を下回っている。
新地金需給・価格見通し・・・・・・三菱商事軽金属販売
2001年は47万㌧の供給不足
年央までに1800㌦の上値挑戦
三菱商事軽金属販売・軽金属原料第一部(古田秀生部長)はこのほど、「2001年のアルミ新地金の需給及び価格動向予測」を発表した。昨年に引き続き、「米北西部の電力コスト高」と「米国景気の減速懸念」という強弱相反する材料を背景に、西側全体では47万㌧の供給不足(2000年見込みは34万7,000㌧の供給不足)を予測。LME3ヵ月先物は今年1~3月期:1450~1750㌦・平均1600㌦、4~6月期:1500~1800㌦・平均1650㌦と予想、「年央までは上値を試し、それ以後は若干下値を試す展開が予想されるなど、振幅が激しく、上値の重い相場になる」としている。
1.2001年の需給動向
(1)需要見通し
アルミ相場の牽引役である米国景気の減速により、主要なアルミ需要分野である自動車及び住宅の販売に影響すると考えられるため、2001年における米国のアルミ需要はここ数年の大幅な伸びに比べ減速傾向が鮮明になることが予測される。
一方、米国以外の国は米国経済減速の影響を受けて2000年の伸びには及ばないものの、欧州は主要需要国であるドイツ、仏などの経済成長の安定などから需要堅調、日本や東南アジアについては引き続き回復基調をたどると考えられることから西側全体のアルミ需要は、前年比2.6%増の2,074万9,000㌧を予測。
(2)供給見通し
2001年の西側生産量は、新規増設などによる生産増78万㌧や電力コスト上昇による北米プロデューサーの減産を考慮に入れて、昨年実績見込みの1,759万9,000㌧比1.6%増の1,787万9,000㌧を予測。これに東西貿易による西側の入超240万㌧を加え、西側全体の総供給量を2,027万9,000㌧とした。
この結果、2001年の需給バランスは47万㌧の供給不足になると予測している。
2.相場見通し
米国経済の減速によりアルミ需要の伸び率低下が想定されるものの、年明け早々に実施された緊急利下げなど米国政府によるハードランディング回避のための努力により、アルミ相場の急落の可能性は低いものと思われる。
一方、相場を押し上げる材料としては、①電力コスト上昇による北米プロデューサーの追加減産②需給タイト化がみられる銅相場のさらなる価格上昇にアルミ相場が追随する可能性③ロシアのアルミプロデューサーの業界再編による供給不安--などがあり、これらの影響により大きく値を上げる可能性もある。ただ度重なる相場急騰場面では断続的なプロデューサーの先物売りにより相場高騰が抑制されることや、来年はさらに米国のアルミ需要の伸び率低下が予想される。
このため、年央までは上値を試し、それ以後は若干下値を試す展開が予想されるなど、振幅が激しく、上値の重い相場になろう。
図・表・写真は本誌でご覧ください。

|