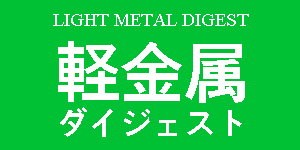
このサイトは、本誌の定期購読契約者のみが利用できるメンバー専用ページです。
 |
NO.1526(2001年03月12日号)
|
YKKAPアメリカ社
供給不足解消へ大型機増設
明春稼働で両肺操業体制
YKKAPアメリカ社は2001年度に大型押出機1基を増設する。吉田忠裕社長がこのほど明らかにしたもので、米国の旺盛な建材需要に対応する。これにより同社は押出機2基による両肺体制となり、量産効果と生産性向上、コスト低減が図られる。
YKKAPアメリカ社(ジョージア州アトランタ市、資本金5,500万米国ドル、山本義広社長)は、アルミ建材の海外一貫工場として、1986年のインドネシア「YKKアルミコ・インドネシア」に続く2番目の会社で、1991年に米国に設立。工場はジョージア州ダブリン市に保有し、アルミ溶解・ビレット鋳造・押出・表面処理・切断加工の素材から長尺形材製品までの一貫体制を整え、翌1992年から量産を開始。
同プラントの心臓部に当る押出設備は、YKK製の2,200㌧押出機1基で、アルミ押出材の年産能力は公称6,000㌧。この一貫ラインは当初から押出機2基を想定して設計、一部先行投資されていたため、量産効果とコストダウンが期待できる2基目の導入のタイミングが現地サイドの課題となっていた。
生産品目は主としてストアフロント用のアルミ長尺形材、ビル建材用形材など。吉田忠裕社長によると、「米国景気はIT産業の成長率鈍化などで先行きが懸念されているが、建材需要は好況が続き、YKKAPアメリカ社は能力を大幅に上回る高操業が続いている」という。こうした供給能力不足解消と将来の販売拡大策を目的に押出機を増設するもの。近く詳細計画をまとめたうえで今年夏頃に着工、2002年春には操業開始の見込み。ストアフロント用大型形材の需要が増えているので、現有の2,200㌧を上回る3,000㌧から4,000㌧の大型機になるとみられる。増設後の形材生産能力は1万2,000㌧に倍増する。
YKKAPアメリカ社は現在、ジョージア州など米国南部を中心に7ヵ所の営業拠点を持ち、店舗フロント加工業者に長尺形材を供給している。吉田社長によると「2004年には営業拠点を中西部まで拡大、14~15ヵ所に増やす」倍増計画があるという。ファスニング事業同様に建材事業においても世界戦略を展開しているYKKグループだが、米国におけるアルミ建材事業は米国上陸10年目にして本格軌道に乗った。
なお、YKKAPの建材関連の海外子会社はYKKAPアメリカ社、YKKアルミコ・インドネシア(押出機4基)の二つの一貫工場のほか、建材加工工場としてYKKAP香港社(アルミ建材)、YKKAPシンガポール社(同)、YKKAPマレーシア社(同)、YKKブラジル社(ファスナー・アルミ建材)、YKK台湾社(同)、大連YKKAP(樹脂サッシ)がある。これらの工場へはYKKアルミコ・インドネシア社から形材を供給していたが、米国の増設が完了すると、ブラジルなどへは米国から供給することになる。
アルミネ
三隅に大型伸線機2台新設
径9.5㎜から0.8㎜まで一貫で
アルミネは三隅工場に大型伸線機を導入する。電子部品向けの需要増に対応するもので、径9.5㎜から0.8㎜まで一気に伸線することが可能になる。また、川上西では自動車向け鍛造用定尺棒の需要増を受けた設備対応を行う。
アルミ線・棒材メーカーの大手、アルミネ(大阪市西区阿波座、竹内正明社長)は電子部品、自動車部品向け需要増に対応した設備投資を実施する。三隅工場(山口県大津郡三隅町)では今年3月稼働予定で、大型伸線機2台を導入する。投資額は約3億円。
現在同工場は大型伸線機2台(線径9.5㎜から3㎜に伸線)、中型伸線機4台(3㎜から0.5㎜に伸線)を保有、月産能力は600㌧。
今回、既存の大型伸線機1台と中型伸線機2台を売却して、線径9.5㎜から0.8㎜まで一気に伸線が可能な大型機2台を新たに設置する。電子部品向けに需要が増加していることに対応するもので、生産能力は月800㌧にアップする。さらに従来2工程で行っていた伸線を1工程にすることでオペレータ要員減や品質管理の効率化など、トータルでのコスト削減も見込めるという。
また、川上西工場(山口県阿武郡川上村白上)では約1億円を投じて、ドローベンチ(引き抜き加工機)と口付け機各1台を導入する。稼働予定は今年5月。自動車向け鍛造用棒の需要増に対応したもので、直径75㎜から25㎜の鍛造棒が製造可能となる。同工場は現在、直径75㎜から20㎜の棒材をコイルで出荷しているが、定尺棒の需要が拡大していることから設備対応を行なうもの。同工場では現在月産600㌧の棒材のうち、300㌧を定尺棒で出荷する予定。
インターンシップ制度を活用
意欲ある学生採用で、日軽金
日本軽金属は新卒学生の採用活動の一環として、インターンシップ制度を積極的に導入する。即戦力と専門性を備えた学生の効率的な確保を目的に、対象大学、受け入れ人員の増加や期間の長期化など同制度を見直して採用とのつながりを強めた内容とする。
インターンシップ制度は大学生が一定期間キャンパスを離れて企業などで就業経験を積むもの。学生にとっては自己適正や自己発見、将来の進路設計を考える絶好の機会になるため、社会貢献の一環として同制度を行う企業が増えている。日軽金は平成9年から、4年制大学の2年生を対象としたインターンシップ制度を導入。今年もフェリス女学院大学の2年生2名を受け入れ、2月13日~26日の約2週間、広報・IR室およびグループ・メタルセンターで業務体験を行った。
こうした制度はここに来て、自分のライフスタイルや就業観にあった企業を選択したいという学生と、意欲のある学生を効率的に採用したいという企業側の利害が一致、新しい就職・採用活動として注目されている。
日立金属・アルミホイール事業
日米の増産対応、ほぼ完了
高意匠・付加価値品で採算重視
自動車メーカーからのコスト削減要求が依然厳しい中で、日立金属は数量拡大よりも高意匠・高付加価値製品を主体に採算・収益重視の販売姿勢を貫く。
アルミホイール大手の日立金属は、予て進めて来た日米両生産拠点の増産対応をほぼ完了した。国内生産拠点である熊谷軽合金工場(埼玉県熊谷市)の生産能力は月20万個。一方、米国の生産拠点であるAAPセントメリーズ(オハイオ州)は16万5,000個の体制が整った。
同社は98年下期以降、生産能力を当時の300万個/年(日本180万個・米国120万個)、25万個/月(日本15万個・米国10万個)から、日本・米国両拠点とも月産20万個、年産480万個の生産体制構築を目指して、逐次設備増強を図ってきた。
販売実績は99年度(2000年3月期)の国内200万個、米国120万個に対し、今年度は一部OEM納入について、値下げ要求への対応として受注量を抑えたのに加え、米国自動車販売の急減速に伴って「昨年末以来、需給タイト感が緩和してきた」ため、国内が当初計画である220万個を下回る200万個弱、米国が180万個程度となる見込み。2002年3月期は国内で180万~190万個の販売を予想。下期には米国自動車販売の回復期待や、供給量を抑えている一部OEM受注の再開を見込む。
米国生産拠点はライン変更で20万個まで生産能力を引き上げることが可能な設備対応が完了しているものの、採算を重視した受注を前提に能力アップを図る考えだ。
同社は自動車機器事業部の戦略商品であるアルミホイールの販売では「数量の拡大よりも、17インチの大口径を主体として高意匠・高付加価値ホイールの拡販」を重点志向している。
その一環として、昨年、アルミホイールの開発期間を半減する「短納期開発システム」(Integrated
Design-In
System)を構築。さらに、このほど製造段階での新しいシステムとして「エスキューブ(Super
Sharp Shape)」を開発した。同システムは、同社がこれまでに開発・実用化した鋳造製造技術「HIPAC-Ⅰ・Ⅱ」をさらに進化させるとともに、CAE技術、ITなどを駆使、「現在ある技術を集大成したもの」。
従来のアルミホイールに比べて20~25%の軽量化を実現するともに、抜け勾配が小さいため、メッシュタイプなどの製品で「よりシャープ感が出る」など、意匠性のアップ、デザイン自由度が増すことが特長。熊谷軽合金工場の一部ラインを改造して同システムを実用化。製品がこのほど発売された4WDスポーツセダンに初装着された。
古河電が3ヵ年中期経営計画
軽圧は業界リーディング企業に
古河電工(古河潤之助社長=写真)は2月22日、2001年度から3年間の中期経営計画の概要を発表した。「エクセレント・カンパニーへの挑戦」をスローガンに、ニーズを捉えた新商品開発とイノベーションの推進、グローバルシェア上位を狙える新商品開発への注力、高付加価値事業の実現で連結営業利益率10%以上の確保、成長分野への経営資源のシフト、グローバルサプライヤーとしての海外生産体制強化--などが骨子。
重点テーマは、WDM(波長分割多重伝送)関連を核とする情報インフラ、エレクトロニクス、自動車部品、環境関連など。「過去5年間に市場に出した」と定義する新商品比率を単体ベースで今年度見込みの45%(昨年度28%)から2003年度には65%に引き上げる。そのため、今後3年間に、主に重点テーマに対しての研究開発に750億円、設備投資・M&Aに2,500億円を投じる。グループ従業員数は現在の2万3,000人から3万人体制を確立するが、増員は海外生産体制の強化によるもので、国内の従業員(現業)は大きく変動させない考え。
セグメント別計画では、「マテリアル部門」(伸銅品、電解銅箔、アルミ圧延品)におけるアルミ圧延品については「当社事業の柱の一つに位置付け」(古河社長)、「スカイアルミとの生産連携強化による生産体制最適化、製造コストの削減、新商品開発の強化により今後3年間でシェアの拡大と利益体質の改善を図り、板材でトップシェアの業界のリーディングカンパニー」を目指す。新商品比率については「新商品が出なくて、コストが下がらないものは止めるので、比率は高まる」とし、アルミ板材の新製品例として「高機能性を付加したプレコート材」を挙げた。
昭和アの国内4製造所が取得
環境ISO、マレーシア年内に
昭和アルミニウムの堺製造所は2月7日付で環境ISO14001の認証を取得した。同社はこれまでに、平成10年に彦根製造所、12年に小山製造所、那須製造所が同認証を取得しており、これで国内4製造所がすべて、環境ISOの認証を取得したことになる。
一方、マレーシアのメモリーディスク製造会社、ショウワ・アルミナム・マレーシア(SMS)は昨年12月28日付でISO9002の認証を取得した。同社はISO14001の認証についても年内の取得を目指して活動中。
飲料用アルミ缶国内需要
昨年168億缶、20年ぶり減少
今年も1.1%増と伸悩み傾向に
アルミ缶リサイクル協会(理事長=河野毅昭和アルミニウム缶社長)は2月23日、2000年暦年の飲料用アルミニウム缶需要実績見込みと2001年の予測を発表した。
それによると、2000年の国内需要量は前年比0.9%減の168億缶となる見込み。ビール消費量の低迷とペットボトルの台頭でアルミ缶の国内需要は97年以降伸び悩み傾向にあるが、前年比マイナスは81年の12%減以来20年ぶりのこと。2001年の予想も169億9,000万缶、1.1%の微増にとどまる。
昨年の国産缶出荷量は164億缶(前年比1.3%減)。内訳では、発泡酒を含むビール用が2.0%増の104億2,000万缶。昨年のビール類(ビール及び発泡酒)の国内消費量は前年比0.7%減。22.1%を占める発泡酒が前年比15.2%増と大きく伸びたものの、ビールのみでは4.5%減となり、「ビール市場は成長が止まっているのが現状」(河野理事長)。ただ、アルミ缶化率が100%近い発泡酒の販売が好調なため、ビール缶化率は2000年には58.4%と、98年の54.0%、99年の57.0%から着実に上昇、ビール向けアルミ缶の出荷増につながっている。
一方、清涼飲料、低アルコール飲料(缶酎ハイなど)などの「その他」向けは59億8,000万缶、前年比6.4%減となる見込み。500mLの小型ペットボトルの増加が主因で、とくにペットボトルの比率の高い、お茶など「水系」飲料が好調なことが影響した。小型ペットボトルの今年の市場規模は前年比2~3割増の70億本前後になるとみられている。
続く2001年の国内需要量は169億9,000万缶、前年比1.1%の微増予想。ビール向けが104億3,000万缶、昨年比0.1%の横ばい。一部スチール缶が採用されているものの、アサヒビールの発泡酒参入もあり、ビール缶化率は59%前後と若干アップするものの、ビール消費量の伸び悩みを折り込んだ予測。
一方、ビール以外の飲料向けは61億7,000万缶、前年比3.2%増の予想。キャップ付きボトル形状缶の伸びに期待している。ボトル缶の需要量は「2000年1億缶、2001年10億缶程度」(河野理事長)という。
新日軽社長に長谷川日軽常務
新日軽は2月23日開催の取締役会で、長谷川和之日本軽金属常務執行役員の社長就任を内定した。4月1日に正式就任する。中西雄三取締役会長は相談役に、また米持謙三社長は取締役会長に就任する。経営トップ層の刷新と活性化を図り新体制の下で建材事業の構造改善策を遂行する。
長谷川和之(はせがわ・かずゆき)氏の略歴:昭和15年8月生れ▽35年日軽金入社▽40年明治大学政経学部卒業▽63年資材部長▽平成7年4月加工製品本部パネルシステム事業部長▽同6月取締役▽11年常務取締役▽12年常務執行役員。
インテリア断熱サッシを一新
アルプラ70M・S、新日軽
新日軽はこのほど、木造戸建住宅用窓としてインテリア断熱サッシ「アルプラ70M・S」シリーズを発売した。アルミと樹脂を複合した同社独自の「アルプラ構造」をさらに進化させた「新アルプラ構造」の採用により、断熱・防露・水密性能など基本性能をワンランク向上させた半面、価格はリーズナブルに設定した。
「新アルプラ構造」は室内全面および躯体に接するアングル部を全て樹脂製に、さらに樹脂形材を下枠内部に使用したことが大きな特長。
枠・障子の間には、従来のエアタイト方式に加え、上框はダブルタイトの採用により気密性・断熱性をアップ。断熱性能は、低放射複層ガス入り一般アルミサッシの約3倍(2.33W/㎡K)、一般複層ガラス使用時で約2倍(3.49W/㎡K)を実現した。また遮音性能も一般複層ガラス(3-A12-3)仕様でT-1(25)等級。下枠内を排水する新排水機構により水密性もW-4(35)等級と向上した。
内観色は木粉入り樹脂を使用した「Mシリーズ」と、新色ホワージュの「Sシリーズ」の2種類。外観色と併せて、外壁と住宅デザイン、部屋のインテリアなどとのコーディネイトが可能。
部材標準価格は生産体制の充実と細部にわたるコスト追求により引き違い窓1717(幅1690㎜×高さ1787㎜)の場合で「アルプラ70Mシリーズ」が7万7,100円と従来品の「アルプラ70MW」の8万4,700円に比べプライスダウンを実現。同社では初年度30万セットの販売を目標にしている。
昭和ア合併後のアルミ事業
昭和電工が新体制を発表
昭和電工は3月30日の昭和アルミニウム(小島巖社長)との合併に伴う組織改定を次の通り発表した。
①従来の「石油化学」「化学品」「無機材料」「エレクトロニクス」の各事業部門に加え、新たに「アルミニウム材料事業部門」、「アルミニウム加工品事業部門」を設置。両事業部門配下に、それぞれアルミニウム材料事業企画部、アルミニウム加工品事業企画部を設置。また、現在昭和電工アルミニウム事業部の地金グループを「メタルセンター」、ショウティックグループを「ショウティック事業部」とし、とともにアルミニウム材料事業部門配下に。
②現行昭和アルミの圧延品事業部、箔事業部、押出品事業部、SADプロジェクト、堺事業所(堺製造所を改称)、彦根事業所(彦根製造所を改称)をアルミニウム材料事業部門配下の組織に。
また、昭和アルミの情報機器部品開発部、熱交換器事業部、OA機材事業部、パネル事業部、アルミ缶営業本部、小山事業所(小山製造所を改称)、那須事業所(那須製造所を改称)はアルミニウム加工品事業部門配下の組織に。
③昭和アルミのMD事業部(メモリーディスク事業部を改称)をエレクトロニクス事業部門配下に。
④スタッフ部門の組織は現行昭和電工と同様。また、昭和電工の技術研究本部配下に「アルミニウム技術研究センター」を、生産技術本部配下に「アルミニウム生産技術部」を設置。アルミニウム技術センター配下に「堺研究室」と「小山研究室」を設置。
昨年のアルミ器物輸入量
11%増、初の3万㌧突破に
財務省通関統計によると、2000年暦年のアルミニウム器物輸入実績は数量で3万668㌧、前年比11.1%増と2年連続で過去最高を更新、初の3万㌧台乗せとなった。ただ、金額では185億3,700万円、同0.3%増の微増にとどまった。トン当り単価は60万4,000円で前年の67万円に比べ9.9%、98年の75万7,000円からは25.3%のダウン。
日軽金が4月から本部制廃止
新商品・事業開発で新委員会
日本軽金属は佐藤薫郷新社長就任に伴う4月1日付機構改革を発表した。それによると、本部制を廃止し、上席役員による管掌制に変更する。事業部を社長直結として機動力を高めるとともに事業部長の執行責任を明確にするのが狙い。東洋アルミ本部廃止により「東洋アルミ事業部」を、技術・開発本部廃止により「技術・開発グループ」が新設される。
さらに、新商品・新事業による収益力拡大を加速させるため「商品化事業化戦略委員会」を新設する。同委員会は、これまで組織上明示されていなかったクロスファンクショナルな開発組織(横串開発グループ)を明確に位置づけるもので、委員長には佐藤薫郷社長が就任。日軽金グループ全体の開発活動を企画、推進、有望分野において日軽金グループが有する資源を最大限に活用する。
ソーラー電動エクテリアに
新機種追加、東洋エクス
東洋エクステリアは、ソーラーエネルギーで稼働する電動エクステリア「陽動シリーズ」に車庫用シャッター「フレームシャッター」=写真=と伸縮門扉「アルピタGX」の2機種を追加・新発売した。初年度販売目標は1億円。
「陽動シリーズ」は電気工事(AC100V引き込み工事)が不要なDC12V仕様のエクステリア専用ソーラーシステムを搭載した業界初の商品として昨年4月から発売している。
日軽金の人事異動
(3月26日付)退任・日本アマゾンアルミニウム取締役に就任、常務執行役員メタル・産業部品本部担当・大辻孝雄(4月1日付)代表取締役社長・商品化事業化戦略委員会委員長、佐藤薫郷▽副社長執行役員資材部・経理部管掌、中国担当、取締役・平塚喜郷▽同グループ営業促進担当、景観製品部、名古屋支社管掌、大阪支社長、取締役・林昭彦▽常務執行役員板事業部・押出事業部・軽圧加工事業部・電極箔事業部管掌軽圧技術開発部長、石山喬▽同苫小牧製造所管掌、総務部長、小林基▽同メタル合金事業部・熱交事業部管掌、素形材事業部長、比企能信▽同グループ・メタルセンター、蒲原製造所管掌、総合企画部長、堺隆道▽執行役員熱交事業部長、和佐寿一▽同化成品事業部長、石原充▽同経理部長、栗原慶明▽専務執行役員退任、取締役開沼章夫▽常務執行役員退任、4月1日付で新日軽社長に就任、長谷川和之▽執行役員退任、4月1日付で日軽物流社長に就任、松井英二▽執行役員退任、4月1日付で理研軽金属工業社長に就任、遠藤秀夫▽東洋アルミ事業部長、取締役兼専務執行役員垣谷公仁▽技術・開発グループ長、常務執行役員河村繁▽化成品事業部管掌、常務執行役員原廸夫▽技術・開発グループ操業改善担当、執行役員宮内洋治▽技術・開発グループ環境保全室長、執行役員田島弘二▽技術・開発グループグループ技術センター長、執行役員宮下輝雄▽板事業部長、執行役員川上耕二▽電極箔事業部長・東南アジア担当、執行役員中嶋豪。
図・表・写真は本誌でご覧ください。

|